MENU
三洋化成ニュース No.498
2016.09.05

1973年、京都市生まれ。京都女子中学・高校から日本大学文理学部へ。
在学中は、陸上短距離選手としてインターハイ、国体などに出場。その後、スポーツ心理学を学び、ノーザンアイオワ大学大学院で修士、ノースカロライナ大学大学院グリーンズボロ校で博士課程を修了。兵庫県立大学環境人間学部准教授などを経て、現職。シンガポールのセーリング代表のオリンピック出場など、各国で幅広く、メンタルスキルを中心としたコンサルテーションを行い成果をあげる。高校・大学の部活動や、アスリート・指導者、企業などへの講演・セミナーも多数手がける。2012年から2015年まで、エディー・ジョーンズ前ヘッドコーチ(HC)に請われて、ラグビー日本代表のメンタルコーチを務めた。
写真=本間伸彦
2015年の第8回ラグビーワールドカップで、24年間勝ち星のなかった日本代表が、当時世界ランキング3位の南アフリカを破りました。その際、メンタルコーチを務めていたのがスポーツ心理学者の荒木香織さんです。五郎丸歩選手がキックの前に必ず行っていた「プレ・フォーマンス・ルーティン」を、ともに作り上げた立役者としても知られています。学問を裏付けとしたメンタル強化の手法と、選手たちを心理的にサポートした細やかな心配りについて、お話を伺いました。
-- ラグビーワールドカップで日本代表が南アフリカに勝ったのは2015年の9月ですが、今でもよく覚えています。日本のみならず世界のラグビーファンが驚き、日本代表のプレーに熱狂して、「大番狂わせ」「奇跡の勝利」と報じられていましたね。
南アフリカ戦は、勝つつもりで準備していたんで、私たちは奇跡なんて思ってないです。エディー・ジョーンズ前ヘッドコーチ(以下HC)は、本気で日本代表をベスト10にするという目標を掲げて、また勝たすノウハウを持っていました。その一つが、スポーツ心理学でした。HCは、初めてラグビー日本代表にメンタルコーチを導入した人なんです。
-- 日本のスポーツ界で、メンタルトレーニングが重要視され始めたのはいつ頃ですか。
まだ重要視されてないと思います。スポーツ心理学では、スポーツや運動の場面におけるパフォーマンスと心理的傾向の関係などについて、調査や統計を重ねて検証し、解き明かしていきます。理論を基にして、試合に臨む前の心の整え方などのスキルを、アスリートに伝えるものなんですよ。
-- 海外では、スポーツ競技にメンタルコーチが付くことが多いのでしょうか。
スポーツに力を入れている国では当たり前ですね。でも日本では、学問を基盤にしてない自称メンタルコーチも多いんです。一方で、日本スポーツ心理学会の認定する、スポーツメンタルトレーニング指導士もいますが、大学での研究をメインにしていて現場にあまり足を運ばない指導士も多く、成果があがりにくいのが現状です。
-- 荒木さんは、どんなきっかけでスポーツ心理学を学び、メンタルコーチになられたのですか。
私は、社会人1年目まで、陸上競技の短距離の選手だったんです。記録は全国でトップクラスなのに、大会でなかなか満足できる結果を出せませんでした。就職はしたものの、陸上競技ばかりやっていたので社会のことを知らなすぎると感じて、アメリカに留学。8年間スポーツ心理学を学びました。そこで、選手時代の私に足りなかったものは心の準備だったとわかったんです。スポーツ心理学に基づいて、周囲からの期待の受け止め方、不安への対処の仕方などを教えてもらっていたら、私の選手としての結果は違っていたかもしれない。このスキルを学んで次代のアスリートたちに伝えたいと思って、コンサルテーションの仕事を始めました。
-- HCからは、どんな依頼を受けたんですか。
「マインドセットを変えてください」って。マインドセットっていうのは、考え方や受け止め方、情報の受け取り方・発信の仕方、調整の仕方、つまり全部ですよ。「脳みそ総入れ替えしてくれ」っていう感じ(笑)
-- すごい依頼ですね(笑)。よく引き受けましたね。
ちょっと迷いました。でも、このような仕事で女性がチャンスをいただくことって少ないので。
-- HCは、アシスタントコーチを選ぶ際に、ご自身より知識豊富な人を選ぶそうですね。
なぜ私を選んでくださったのか、いまだによくわからないんですが。海外で10年以上生活しているので、日本人と外国人の考え方がわかっていたことが、大きいかもしれません。スポーツでの、選手とコーチの関係や、選手がスポーツに取り組む姿勢は、日本と海外で全然違うんです。HCとの面接の時に、日本人の良いところや、世界で戦っていくために何を変えていかなければならないか、などについて聞かれました。ほかにも、英語と日本語ができるので、外国人コーチと選手の両方とコミュニケーションできること、スポーツ心理学を大学院で学びコンサルテーションの基盤にしていること、元アスリートなので現場を知っていること、などが選んでいただいたポイントだと思います。
-- 「マインドセットを変える」ために、最初どんなことから手を付けたのですか。
まず観察することからでしたね。観察していくつか挙がった課題のうちの一つが、チームの基盤となる、ラグビーに対するモチベーションや誇りでした。その頃のラグビー日本代表はワールドカップで負け続けていて、代表に選ばれても世界では勝てないだろうし、所属する国内チームの練習以上にやらなきゃいけないことが増えるし。選ばれることが名誉に思えない環境なので、招集を断る選手がいたくらいです。そこで、まず日本代表として選手たちのアイデンティティーを作り上げる作業に取り組みました。出身国がさまざまな選手たちと話し合うと「日本という国の名前を背負う心の準備として、『君が代』をきちんと歌ったほうがいい」というアイデアが出てきて。それで、日本語の読めない選手のために歌詞をローマ字で書くところから始めました。
-- そうか、そこからなんですね。
私たちが選手に「これをやれ」と押し付けたところで何も変わらないんです。大事なのは、どうすれば選手たちが主体的に課題に取り組んで解決できるか。私は、その過程が、スポーツ心理学の理論に基づいた活動になっているかどうかチェックしながら一緒に進める。それを4年間続けました。
-- 選手たちとの話し合いのなかで出た思いやアイデアをヒントにして、荒木さんのスポーツ心理学の知識と合わせて、「これでいってみよう」となるんですか。
主にリーダークラスの選手たちと話し合っていましたね。ほかに、日本と海外の文化の違いや、選手の教育のされ方の違いを、HCと選手の両方に伝えるのも大切でした。HCがどういう思いで発言しているか、そこまで通訳の方は伝えきれないので。
-- HCやコーチの指示がどうもうまく伝わってないな、というのを荒木さんは隣で見ているんですか。
現場で見ていたり、後から聞いたり。コミュニケーションがうまくいかなくて、HCも選手もそれぞれわだかまりを抱えている時に、お互いの言い分を聞いて、誤解を取り除き、コミュニケーションをスムーズにしていきます。

-- お互いの気持ちを理解して、交通整理するんですね。
HCはよく、「日本で育った選手は『はい』と返事はするが、理解していないことが多い」と言ってました。そもそも「とにかく走れ、当たれ」という練習をずっとしてきたので、考えるプレーに慣れていなかったんです。そこでメンター制度を採り入れて、選手同士で、今日の練習の目的を確認したり、良かったところや改善すべきところを振り返ったりしました。また、わからないことがあったら聞ける環境づくりにも力を入れました。選手がわかってなさそうな顔をしてたら「ほら、聞く聞く!」って。日本人は特に「わからないことがあるのは自分が無能だからだ」と思っちゃうんです。
-- 実力が落ちると、日本代表から外されてしまうこともあるんですか。
そうなんです。厳しい環境なので、周りの評価やほかの選手を気にしてしまう選手も多いんですが、そのせいでミスを繰り返してしまうんだったら、他人と比較しても意味ないですよね。それより、自分がどれだけ成長したかを見たほうがいい。選手には、「何か言われても、『言うとけ!』って思っとき」と。
-- なかなか、そんなふうには思えないんじゃないですか。
だから、結局受け止め方の問題。楽観性って大事なんです。注意された時に「俺はダメだ、外される」と思うか、「これさえできるようになれば残れるんだ」と考えるか、その差ですごく変わりますね。叱られた選手には、「大丈夫、言われたということは見てくれてるんやから、これさえクリアできたら残れる」と言うと、「絶対そうです、頑張る」って言ってましたよ。
-- 荒木さんの活動は、学問の裏付けのあるコンサルテーションである一方で、スポーツマンガに出てくる女子マネージャーみたいに、選手たちの心の支えにもなっているんですね。
「いるだけでええねんで」って、よく言われました(笑)。
-- 学問の理論と、女性らしい細やかな気配りと。両方必要な仕事を成し遂げてくださったことが、同じ女性としてうれしいなと思います。
-- 「考えるプレー」というお話もありましたが、選手たちが自分で考え、自分で決めるようになったことが南アフリカ戦の勝利につながったんですね。
あんなにドラマチックな勝ち方をするとは思ってなかったですけど。試合の最後、HCはショット(ペナルティーゴール)を指示して、強豪の南アフリカ相手に引き分けに持ち込もうとしたんです。でも、選手たちは全然その指示を聞く気がない(笑)。「歴史を変えるの誰ー!?」ってめっちゃ盛り上がってて、自分たちでスクラムを組んで、トライを取りにいこうとしてるんです。五郎丸選手も全く蹴る気ないし。HCはすごく怒ってました。そのうち観客も日本の応援をし始めて、トライが決まって。すごかったです。
-- 決断力や、チームメイトを信じることや、勝てるって信じることなど、メンタルで支えられた部分が大きいですよね。「南アフリカに勝つなんて無理だ」と思ってたら絶対勝てませんものね。
そうなんです、全部必然。勝つための完璧な体制で臨んでいるんで。HCが事前に徹底的に試合内容を分析し、皆で共有しているんです。相手チームの選手一人ひとりの強み弱み、試合会場でお互いの声が聞こえない場合にどうするか、その試合で笛を吹くレフェリーの癖、グラウンドの風向きや芝の状態、など。だから現場で動揺せず、落ち着いて試合に臨めるんです。
-- あの試合を見て、ラグビーってこんなに面白いんだと知った日本人が増えたと思います。
選手主体で日本のラグビーの歴史を変えようということを目標にやってきたので、結果を残せたことで、選手もとても喜んでいました。

2015年W杯が行われたイングランドから帰国する際に選手たちと記念撮影(荒木さん提供)
-- ところで、2年間キャプテンを務めていた廣瀬俊朗選手は、エディーHCにキャプテンを外されてしまったそうですね。廣瀬選手は、代表チームの中で、どう自分の役割を見つけていったのでしょうか。また、荒木さんはどうサポートされたんでしょうか。
もう、HCの答えは変わらないので、廣瀬選手には「決めるのは自分です」と言いました。「代表外れてもいいならそれでもいいし、キャプテンじゃなくなっても、何かチームのためにでも、自分のためにでも、どっちのモチベーションでもいいから、自分で前向きにやっていこうと思うか、それは廣瀬さんが決めることです」と。廣瀬選手はもうちょっと頑張ると決断してくれました。私は、廣瀬選手の細やかなサポートがチームに必要だと思ったので、HCにそう伝えました。
-- 一度チームのトップに立った人が、選手としての評価を受けられなくなって、それでも何らかの役割を自分が果たすと自信を持って言うのは、難しいことだと思います。
キャプテンなど名誉なポジションにいるからとか、試合に出られるからとか、外からの評価をモチベーションにしていると続かないんですよ。だから、廣瀬選手の経験がどれだけ彼自身のためになっているか、満足感や刺激につながっているか、確認し続けました。「今悩んでいることも、将来同じような経験をした人に、今の廣瀬さんの気持ちを伝えてあげられるよ」って。
-- 外からの評価じゃなく、自分の中でそれがどう役に立つかが重要なんですね。
廣瀬選手のような人がいやすいように環境づくりをして、本人にも働きかけて、組織としてやっていけるようにするのが私の役割でした。
-- 「思考停止のテクニック」というものがあるそうですね。私、思考停止というと悪いイメージしかなかったです。
例えば、仕事でミスをした後、そのことばかり考えて、ほかの仕事にも集中できなくて、さらにミスを重ねてしまうことってありますよね。それをストップできるのが思考停止のテクニック。もうやってしまったことをいつまでも考えていても仕方ないじゃないですか。その脳みそのメモリーがもったいない。
-- どうやるんですか。
まず、いつ自分にネガティブな考えが浮かぶか観察するんです。ネガティブな考えが浮かんで自分でコントロールできなくなっていることに気付いたら、ストップの意味のある言葉やしぐさを決めておいて、それをする。指輪を回すとか、「ストップ!」って言うとか、コーヒーを飲むとか散歩に行くとか、やりやすいものでいいです。ストップできたら、その上に、ポジティブな言葉や次にやることを乗せる。
-- 何かストップの意味のある言葉やしぐさを決めておくんですね。
ネガティブなことを思い付いた時とか、言ったり思ったりすることがコントロールできなくなっていた時は、チャンスなんです。ストップして前に進めるようになるから。ただ間違ってはいけないのは、根本的な問題を考えないように、蓋をしてしまう方向に使ってはダメです。
-- 最後に、荒木さんのこれからの目標を教えてください。
スポーツ心理学者の三本柱といわれている、研究活動と教育活動とコンサルテーションを三つとも続けながら、いろいろな方に、確実に結果の出るプログラムを提供していきたいですね。あとは、スポーツを盛り上げていくことを通して、たくさんの方に、勇気や感動やスポーツの良さを伝えていきたいと思います。
-- 期待しています。本日は、ありがとうございました。
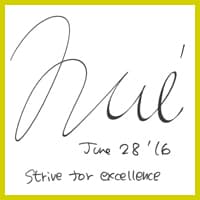
と き:2016年6月28日
ところ:東京・日本橋の当社東京支社にて