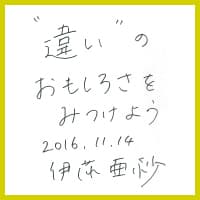異なる視点から異なる世界を見てみたい
-- 伊藤さんの著書『目の見えない人は世界をどう見ているのか』を読ませていただきました。美学を専攻している伊藤さんが、なぜ、見えない人の世界に興味を持たれたのですか。
小さい頃から生き物が好きで、中学生の時、本川達雄さんの本『ゾウの時間ネズミの時間』を読んで、衝撃を受けたんです。自分と全く異なる体を持つ生き物が、どんなふうに世界を知覚し、どんな時間感覚で生きているか、身をもって想像させてくれる内容でした。自分以外の生き物に変身して、その視点から世界を見てみたら楽しいだろうなと空想していましたね。生物学者を目指して、大学では生物学系の学部に進んだのですが、生命を情報化してDNAを読み解くことが中心で、私のやりたいこととは違うように感じました。そこで文系に転向し、美学を研究することにしました。
-- 美学のどのようなところに引かれたのですか。
美学は、感覚的なものや芸術など、言葉にしにくいものについて、あえて言葉を使って解明していこうとする学問です。「私にとって美しさはこういうもの、あなたにとってはどうなの?」というように、その人その人の感じ方を言葉にする時の、その言葉を提供するのも美学の役割です。私は美学を研究するに当たって、感覚的なものや世界観が自分から遠い世界、つまり、私たちが最も頼っている視覚を取り除いた世界は、どのように見えるのだろうと思ったんです。それは、単にアイマスクを着ければわかることではなく、私たちと同じものを知覚するのに、視覚ではない方法を使っている人たちが、どんなふうに世界をとらえているのかを、知るということです。
-- 見えない人に興味を持たれて、その後どのようにして、見えない人と出会おうとされたのですか。
研究の初期に「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」という、暗闇を体験するエンターテインメント施設に行きました。真っ暗闇の中を、数人のグループで歩いていくと、途中に段差や傾斜などの仕掛けがあるんです。落ち葉を踏んだ時の音や感覚はとても新鮮でした。
-- その時、印象に残ったのはどんなことでしたか。
暗闇の中では必死なので、隣にいる初対面の人と手をつないで歩いていました。また、声を出さないと自分の存在が消えてしまうような気がして、ずっとしゃべっていましたね。暗闇の中では普段の自分と違う自分が出てくるんです。それが怖いと同時に、すごい解放感がありました。アトラクションの最後に電気がついた時、ふっと我に返って感じたのは気まずさでした。今まで手をつないでいた人の顔を見て、暗闇にいた時との印象にギャップを感じてしまったんです。相手も気まずかったのか、突然改まって名刺交換をし始めました(笑)。見えるって何だろう、見えることで壁ができるってどういうことだろう?と思いましたね。
-- 見えることで、急によそよそしくなってしまったわけですね。
「見える」というのは便利だけれど、壁にもなります。見えないことでいろいろなことが変わるんだな、と感じました。

学生たちとのワークショップ風景
見えない人に対して作り出してしまう壁
-- 伊藤さんは、見えない人と直接交流して得た学びをもとに、研究されているのですね。見えない人について、認識が違っていたなと思われた点はありますか。
寡黙な人が多いのかと思っていましたが、そうではありませんでした。見えない人にインタビューを始めた当初、会話をリードしなければならないと気負っていましたが、相手は私が緊張しているのを察して、冗談を言って笑わせてくれました。見えない人は声でアピールするしかないので、上手に話そうとする意識が高いように思います。
-- 健常者が見えない人に「助けてあげよう」という意識で接すると、見えない人との間に壁ができてしまうのですね。私も、街で視覚障害の方を見かけると、何かお手伝いをした方がいいのか、いつも悩んでしまいます。
普通に話しかけてもいいと思いますよ。自然な関係が一番です。
-- 子どもは体の不自由な人を見て、「なんであの人手がないの?」などと正直に聞きますが、大人はそれを後ろめたく思って注意しますよね。健常者が、相手を思いやっているつもりで、逆に壁を作ってしまっているように思います。
そうですね。ある全盲の方が「見えなくなってから、毎日が観光バスツアーみたい」と言っていました。周りの人が、見えるものを細かく説明してくれるんだそうです。トイレに入った時にも「ここにトイレットペーパーがありますよ」「ここが鍵ですよ」と。でも本人は、それは触ればわかるし、何より早く用を足したい。「説明しなくていいですよ」と言いたかったけれど、相手が一生懸命なので悪い気がして言えなかったそうです。
-- 親切にしているつもりで、相手を困らせていることがよくあるのでしょうね。目の見えない人をうまくサポートするには、どうしたらいいでしょうか。
私は、肘や肩を貸して、つかまってもらうことが多いです。体に触っていると、次の動きや周囲の状況がある程度わかるそうですよ。説明すること自体が悪いわけではないので、「変わった建物があるよ」というように、普通に会話すると、楽しいと思います。
-- 「右に曲がりますよ」と口で言わなくても、相手は感じ取れるんですね。
ただ、気を付けなければならないのは、見えない人は、それぞれの手法を使って周囲を知覚しているということです。見えない人は、健常者とは違うすごい聴覚や触覚を持っていると思っている人が多いかもしれません。そのような人もいるのですが、感覚を研ぎ澄ますのではなく、どんどん人に聞くタイプの人もいます。見えない人をひとくくりに特別視して接すると、相手に余計なプレッシャーを与えてしまいます。そもそも健常者が、見えない人の「見る」方法に対して「すごい」と言うのは、無意識に見えない人を劣った存在ととらえているから。私は「見る」ためのアプローチの違いを「面白い」ととらえるようにしています。
言葉にすることで見えてくる人それぞれの見方
-- 見える人が見たものを、見えない人に言葉で伝えるには、すべて言葉で説明しなければなりませんね。
難しいですが、やってみると面白いし、苦労して伝わるとうれしいですよ。見えるものを言葉にすることで、見える人同士でも、同じものに対してとらえ方が異なると気付くことができます。これを活かして、見えない人を交えた美術鑑賞ツアーが行われています。一つの作品の印象などを、見える人が見えない人に伝え、話し合いながら解釈を作っていくんです。見えない人の芸術鑑賞の方法としてはほかに、絵を立体的に印刷した触図を使う方法もあるのですが、見えない人の中にはこれは面白さがよくわからないと言う人も多いそうです。
-- 何が描いてあるかはわかるけれど、その絵から受ける印象などはわからないですものね。その鑑賞ツアーでは、見えない人が置いてけぼりになってしまうことはないのですか。
誰かのちょっとした一言で、見方がガラッと変わる面白さは、見えない人も味わうことができるそうですよ。
-- なるほど。逆に見える人が、目をつぶって人の話を聞きながら、絵を想像してみたら面白いかもしれませんね。
やってみたんですが、案外できないんです。最初に全体が与えられていないと、与えられた情報をどこに落ち着ければいいかわからなくて、パニックになってしまいました。見える人は、まず全体をとらえ、それから細部を見ていきますが、見えない人は、部分から全体を想像するんです。例えば机があれば、四隅を触って「これは机で、このくらいの大きさ」という理解の仕方に慣れています。だから、いろいろな情報をとりあえず頭の中に置いておいて、柔軟にパーツを組み合わせて、探偵のように全体を想像するというスキルを持っているんです。
-- 見えない人は、そういう能力を生活の中で使っているんですね。見える人は、もともとあった能力が退化しているか、うまく花開いていない状態なのかもしれませんね。
障害者のスポーツは健常者のそれとは全くの別物

-- テレビでパラリンピックなどの障害者スポーツを観ていると、「目の見えない選手が走ったりボールを投げたりして、怖くないのだろうか」と思ってしまいます。アスリートの皆さんはどのように感じていらっしゃるのでしょうか。
見えない人にとって、スポーツの空間は街中よりも安全です。街中は何が起こるかわかりませんが、スポーツの空間にはルールがあるので、周囲がどう動いているか予測でき、安心して動けるそうです。
-- 障害者スポーツの面白さは、どのようなところにあると思われますか。
健常者のアスリートは、私たちと同じ動きに対して、その速さや正確さなどを、これまでにないレベルにまで高めています。しかし障害者スポーツは、動きそのものが、健常者とは違った原理に基づいているんです。「走る」という動きについても、見えない体、まひの体、義足の体、それぞれの「走る」があります。例えば見えない選手の短距離走には、伴走者が付きます。選手と伴走者はひもで手を結び、ぴったり息を合わせて走ります。スタート位置を調整し、ペースを合わせて進み、コーナーでは、曲がる角度をあらかじめ覚えておいて伴走者が壁となり、コースが外に膨らまないよう選手を押さえ付けながら走るんです。タイムを上げていくには、見える人の短距離走とは全く異なる技術や戦略が求められます。伴走者との信頼関係も大切です。見える人の短距離走とは全く別の競技なんです。
-- 障害者が、健常者と同じ競技にチャレンジしているというわけではないのですね。
障害者スポーツからは、体の新たな可能性を感じます。義足を使っている選手は、義足を自分の体の一部だと感じて走ります。見えない選手は、伴走者との共同作業で真っすぐ走ります。自分以外のものや人とつながり、同調して一緒に仕事を成し遂げているのです。
-- 2020年の東京パラリンピックに向けて、変えていかなければならないことはどのようなことでしょうか。
まず、障害者スポーツに興味を持って試合を見てほしいですね。さらに、スポーツを観戦する方法を作ることで、プレーヤーが増えていくと思います。例えば、日本ブラインドサッカー協会では、目の見えない観戦者にラジオを貸し出して、音声で実況中継を聞けるようにしています。実況も、見えることを説明するだけでなく、選手がそのような動きをした理由とか、周囲の状況、チームの戦略やフォーメーションなどを説明すると、見えない人がイメージしやすいし、見える人にも面白さが伝わります。
-- 障害者スポーツでは、競技そのものの面白さよりも、選手の半生や家族の接し方などがクローズアップされることがありますよね。伊藤さんはどう思われますか。
私は障害に対し、感動でも笑いでもなく「面白い」と興味を持つ姿勢でいたいと思っています。障害を知ることで、健常者の中にある常識や規範、凝り固まった社会の目などが照らし出されるのではないでしょうか。
違いを埋めるより違いを活かす社会へ

-- 健常者が障害について理解を深めることで、障害のある方との間に、より良い関係が生まれていくといいですね。きちんとお互いの違いに目を向け合い、それを言葉にすることが、普通の人間関係をつくっていく第一歩だと思います。お互いの体や障害に関心を持ち、打ち明け合うような関係があっていいはずです。福祉は、見える人が見えない人をサポートするという発想を根幹として、点字ブロックや図書館の朗読サービスなどを整備していきます。この福祉活動も非常に大切ですが、日々の生活の中で、見える人と見えない人の関係が、福祉的な関係にとどまってしまってはいけないと思います。
-- 障害のある方が、暮らしやすい社会にするには、どうすればよいでしょうか。
2011年に公布・施行された改正障害者基本法では、社会の側にある壁によって生活に不自由さを強いられることが、障害者の定義に盛り込まれています。見えないことが障害なのではなく、見えないからやりたいことができない、そのことが障害だというふうに、考え方が変わってきたのです。「障害者」の「害」の字のネガティブなニュアンスを嫌って、平仮名などで表記する動きがありますが、これは配慮しているつもりで、社会の問題を先送りにしてしまっていると危惧しています。
-- 最近、ダイバーシティーという言葉をよく聞くようになりました。人種や性別、価値観などの違いだけでなく、体の特徴についても、さまざまなあり方を受け入れていくことが大切ですね。
障害と無関係な人はいません。誰でも年を取れば、目が悪くなり、耳が遠くなり、足腰が痛み、多かれ少なかれ障害のある体になります。日本がこれから迎える超高齢化社会は、さまざまな障害を持った人が、それぞれの体を駆使して作り上げていく社会だと思います。身体多様化社会と言ってもいいのではないでしょうか。人と人とが理解し合うために、相手の体を知り、想像することが不可欠になってくると思います。
-- ところで、伊藤さんのご専門の、リベラルアーツとはどのような学問でしょうか。
昔でいう大学の教養科目のことですが、その頃の教養科目が知識を得るのを目的としていたことに対して、最近では身につけた知識や情報を社会の中で役立てていく技術を学ぶことに重点が置かれています。2016年度から、先生方と協力して新しいリベラルアーツのカリキュラムを作りました。その一つに、「東工大立志プロジェクト」という科目があります。これは理工系の研究者や技術者を目指して東工大に入学してくる1年生の必修科目であり、自分がこれから学ぶことを、将来どのように社会に役立てていきたいか、志を立てる場なのです。
-- そうしたリベラルアーツや、見えない人の世界からの学びが超高齢化社会に向けて役立つのでしょうね。本日はありがとうございました。
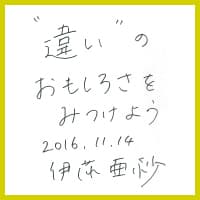 と き:2016年11月14日
と き:2016年11月14日
ところ:東京工業大学大岡山キャンパスにて